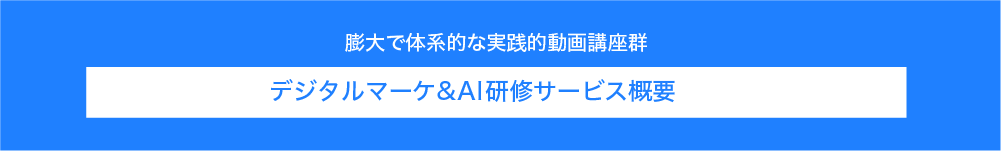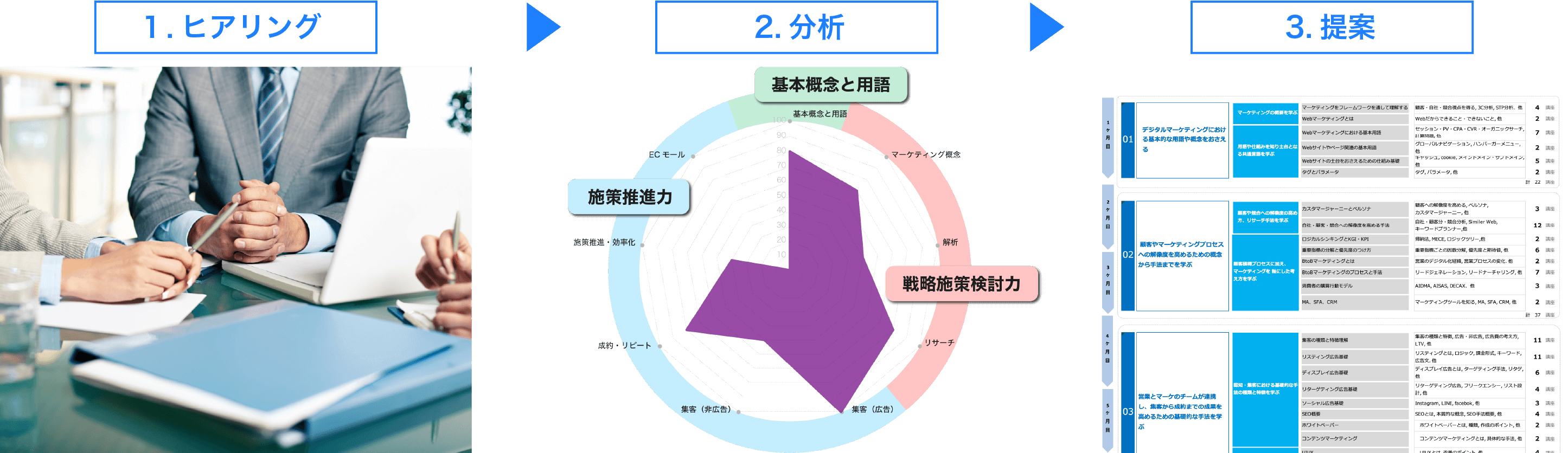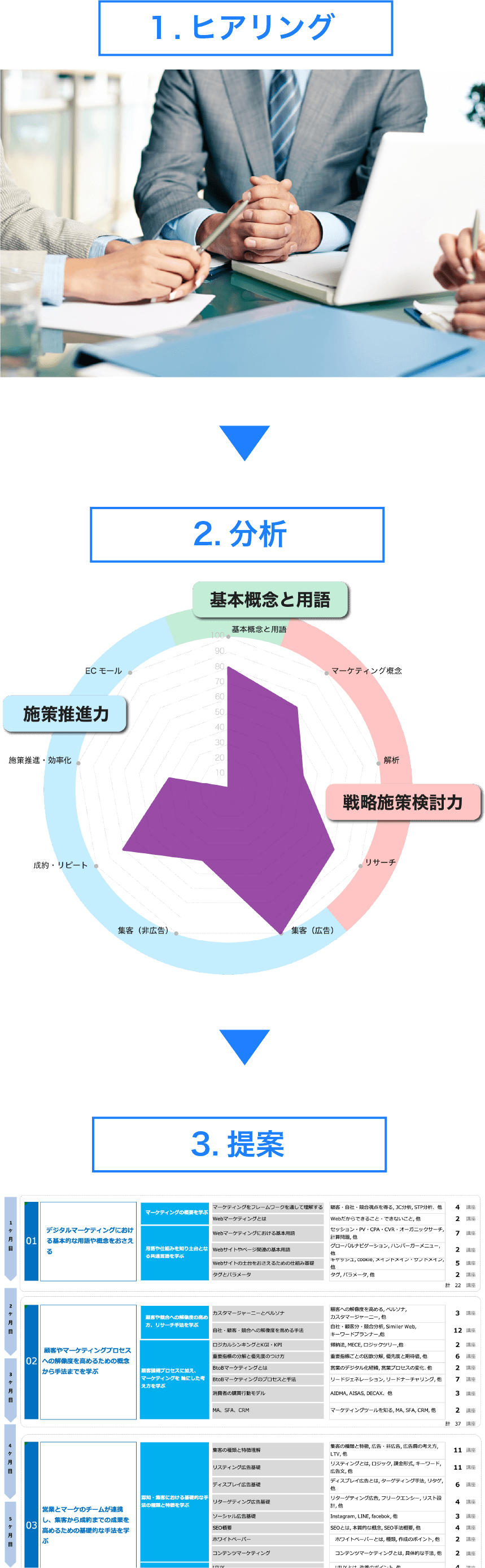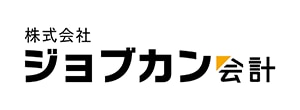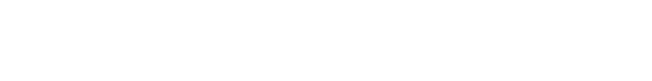デジタルマーケ・AI研修における「【G検定対応講座(7)】AIの社会実装に向けて」のコース概要
コースの概要
AIを現場で活かすための「実践スキル」を身につける
AIをビジネスに活かすには、ただ技術を知っているだけでは足りません。現場の課題にどう向き合い、どのように導入し、運用していくか——このコースでは、そんな“AIの社会実装”に欠かせない実務スキルをじっくり学んでいきます。
まずは、AIを導入する際の目的設定と業務プロセスの見直しからスタート。PoCの設計やBPR(業務改革)を通じて、ただ使うのではなく「活かす」ための考え方を学びます。
プロジェクトをスムーズに進めるためには、CRISP-DMやMLOpsのようなフレームワークの理解も欠かせません。企画から運用まで、現場を支える“しくみ”を整える視点が身につきます。
技術的な基盤としては、PythonやJupyterNotebook、Dockerなど、AI開発に必須の環境にも触れていきます。難しい部分もありますが、初学者でも実践に役立つよう丁寧に解説していきます。
さらに、契約面での知識やPoCの進め方、適切な開発手法の選択など、ビジネスと技術の橋渡しになるような内容も充実。RPAやWeb API、クラウドなど、周辺技術の特徴と役割もしっかり学びます。
データ活用についても、多角的にアプローチします。教師あり学習に必要なアノテーション、オープンデータやコーパスの活用、さらに高品質なデータをどう集めるかまで、実務で役立つ知識を網羅。
そして、見落とされがちな「データリーケージ」のリスクにも触れ、AIを安全・正しく運用するための視点も養います。
AIの企画・開発・導入・運用までを一通り見渡しながら、現場で実装し、成果につなげる力を高める——この講座は、そのための実践的なステップです。技術とビジネスをつなぐスキルを、ここから一緒に育てていきましょう。
コース詳細

<01>AIのビジネス利活用とBPR
この授業では演習問題を通してAIのビジネス利活用と業務プロセス再設計(BPR)について学びます。AIを導入する際には、単なる技術導入ではなく、業務の効率化やコスト削減を目的とする必要があります。また、現行の業務プロセスを見直し、最適化することで、AIの効果を最大化できます。本授業では、AI活用の基本的な考え方やBPRの重要性について解説します。
<02>CRISP-DM, CRISP-ML, MLOps
この授業では演習問題を通してCRISP-DM,CRISP-ML,MLOpsの概要と役割について学びます。CRISP-DMはデータマイニングの標準的なプロセスを示すフレームワークであり、CRISP-MLはこれを拡張し、機械学習の運用や保守を含みます。一方、MLOpsはAIモデルの開発から運用、継続的な改善までを管理する手法です。本授業では、AIプロジェクトの全体的な管理と運用の重要性について解説します。
<03> python、JupyterNotebook、Docker
この授業では演習問題を通してPython、JupyterNotebook、Dockerの概要と役割について学びます。Pythonは、機械学習やデータ分析、Web開発など幅広い用途に利用されるプログラミング言語です。JupyterNotebookは、コードの実行やデータ可視化をブラウザ上で行える環境です。Dockerは、開発環境を統一し、システムの再現性を高めるためのコンテナ技術です。本授業では、AI開発における基盤技術の重要性について解説します。
<04>PoC、契約、開発手法の選択
この授業では演習問題を通してPoC(概念実証)、契約(NDA)、開発手法の選択(アジャイル・ウォーターフォール)について学びます。PoCは、AIプロジェクトの実現可能性を検証する重要なプロセスであり、NDA(秘密保持契約)は機密情報の管理に必要です。また、開発手法にはアジャイルとウォーターフォールという異なる手法があり、それぞれの特徴を理解し、適切に選択することが求められます。本授業では、AIプロジェクトを効率的に進めるための基礎知識を解説します
<05>エッジ、Web API、RPA、クラウドの役割と活用方法
この授業では演習問題を通してエッジコンピューティング、WebAPI、RPA、クラウドの役割と活用方法について学びます。エッジデバイスはリアルタイム処理に適し、WebAPIはクラウド上のAI機能を利用する仕組みを提供します。RPAは業務の自動化を支援し、クラウドは柔軟な計算リソースの確保を可能にします。本授業では、これらの技術を活用する際の特徴や適用範囲を理解し、AI導入の適切な戦略を考える力を養います。
<06>AI利活用のプロセスとオープンイノベーション
この授業では演習問題を通してAIのビジネス活用におけるプロセス設計とオープンイノベーションの考え方について学びます。AI導入時には、既存の業務プロセスを見直し、最適な形で適用することが重要です。また、オープンイノベーションを活用することで、外部技術や知見を取り入れ、開発スピードを向上させることが可能になります。本授業では、AIの社会実装に必要なフレームワークと戦略を理解し、適切な導入方法を考える力を養います。
<07>教師あり学習とアノテーション
この授業では演習問題を通して教師あり学習とアノテーションの基本概念と重要性について学びます。教師あり学習では、AIモデルが正確に学習するために、高品質なデータセットの準備が不可欠です。その中でも、データに正解ラベルを付与するアノテーションは、AIの学習精度を左右する重要なプロセスとなります。本授業では、アノテーションの方法、課題、改善策について理解し、AI開発におけるデータ品質管理の重要性を学びます。
<08>オープンデータセットの活用とデータ収集方法
この授業では演習問題を通してオープンデータセットの特徴と活用方法、データ収集の基本概念について学びます。オープンデータセットは、AIの学習データとして広く活用されており、画像、音声、自然言語処理などさまざまな分野で利用可能です。ただし、ライセンスの確認や適用範囲を理解することが重要です。本授業では、オープンデータセットの活用事例やデータ収集時の注意点について学びます。
<09>コーパスとデータ収集方法
この授業では、コーパスの定義と役割、データ収集方法の基本概念を学びます。
コーパスは、自然言語処理における大規模なテキストデータセットであり、機械学習モデルのトレーニングに活用されます。
また、データ収集では、プロジェクトのROI(費用対効果)を考慮し、センサー技術を活用することで高精度なデータを取得することが可能です。適切なデータの選択と収集は、AIモデルの性能向上に不可欠な要素です。
<10>データリーケージの理解とその防止策
この授業では、データリーケージの定義や発生原因、防止策を学びます。
データリーケージは、モデルの学習時にテストデータの情報が誤って訓練データに混ざることで発生し、モデルの性能が過大評価される原因となります。
これを防ぐためには、データの適切な分割や、特徴量エンジニアリングの際に未来の情報を含めないよう注意することが重要です。
本授業では、具体的な事例とともに、適切なデータ管理の方法を学びます。